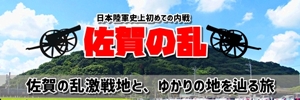佐賀と言えばクリーク(水路)、その水路を利用して作られた集落が今も残っています。
とにかく広い、だだっ広い見渡す限りの平野に田畑がタイルのように並んでいる。私が佐賀を初めて見たとき、一番最初に見た景色でした。佐賀平野は古くから湿地が拡がり、クリークと呼ばれる水路を掘って水を逃がしながら田畑を開墾してきたようです。
白石町肥前犬山城展望台からの眺め。真ん中付近の小山は須古城跡。

また、人が暮らす集落などはクリークを堀として利用し、複雑な迷路のようにして外敵から守っていたのでしょう。実際に佐賀平野に残る城跡は複雑に張り巡らせたクリークを堀とし、郭を浮島のように点在させる構造をしています。
神崎市姉川城跡の航空写真。写真は国土地理院ウェブサイトより。

そんな佐賀の昔の姿を残す場所は今でも各地に点在していて、今回おとずれた鍋島駅近くの若宮神社と周辺のクリークもそんな場所の一つ。佐賀を象徴する、佐賀らしい町並み。
見てくださいコレ、クリークの中に浮島のように建つ若宮神社。いかにも!という景色。

神社自体は大きくないのですが、水に浮かぶ社というのがいいですね。

神社の裏側に回ってみました。

神社の周りには、こんなクリークが張り巡らされているんです。まるで城の水堀です。

神社の裏側にあった畑、完全に浮島状態。堀の中にある土橋を渡らないと行くことが出来ません、まるで城の郭のよう。もとは屋敷が立っていたのかもしれません。

若宮神社周辺は住宅地になっているのですが、この住宅地はクリークに囲まれた迷路のようになっているんですよね。これぞ佐賀の原風景、歴史を感じさせる地形。
若宮神社から少し西に歩くと、集落への入り口がありました。もちろん、クリークにかかる橋を渡って入っていきます。

入り口にあったお地蔵様。

入り口から大きく直角に曲がる道、角に恵比寿像があります。

角を曲がると真っ直ぐに伸びる道。

道を進んでいくと、すぐ途中にまたクリークがありました。

何だか古そうな建物がありますよ、レンガが見事です。

そしてまたクリーク。

ほとんど舗装されていない道

進んでいくと、立派な建物が建っていました。

曲がりくねった道、わき道にそれるとすぐクリークに突き当たって行き止まりになります。外敵が侵入しても、大人数で進むのは難しいうえに制圧するのにも時間がかかりそう。なれてなければ道に迷うので、余所者を発見するのも容易だったでしょう。

狭い路地を抜けていくと、また大きなクリークがありました。水鳥が楽しそうに泳いでいます。

こういうところは昔ながらの風景じゃないでしょうか。

住宅地の中を縦横にめぐらされたクリーク。

住宅地に水路がある事自体は珍しくないのですが、これほどのスケールでドーンと城の堀みたいになってるのは佐賀ならではじゃないでしょうか。

集落の南側には公民館がありました。先に紹介した若宮神社は、もともとこの場所にあったそうです。

公民館の裏側から見たクリーク

最後に今回訪れた集落の航空写真。昔はもっと広い集落だったのだと思われます。一部は埋め立てられているようですね。

写真:国土地理院
佐賀だけではないと思うのですが、田舎の楽しさはこういった昔の地形などが今も残っている事だと思うんです。誰かのブログで読んだのですが、アメリカの経済学者が有名な観光地になるためには100年間建物もそのまま、街並みも何も変えずに維持し、生活様式も100年変えずに続ければ観光地として成功すると言ったそうです。
確かに大正時代の街並みが今もそのまま残り、そこで大正時代の生活をしているような場所があれば有名な観光名所になっている事でしょう。流行を追いかけてあれこれやるよりも、今ある物、今まで残してきたものと当時のストーリーを関連付けて活かしていく。それこそが最大の観光振興策なのではないかと思うようになりました。まあ、観光に向いてる地域と、そうでない地域があるので全てにあてはまる訳ではありませんが。
佐賀には100年どころか中世の姿をとどめている地域や場所が数多く残っています。うまく活かして、残していってもらいたいですね。
最後に、この場所は佐賀ポータルの読者から教えてもらった場所なんです。貴重な情報を頂き、ありがとうございました。
「若宮社」
MAP:佐賀市鍋島町大字八戸溝1365−1(若宮社)⇒ Googleマップへ
最新情報をお届けします
Twitter で佐賀ポータルをフォローしよう!
Follow @SagaPortalCopyright © 佐賀ポータル All rights reserved.